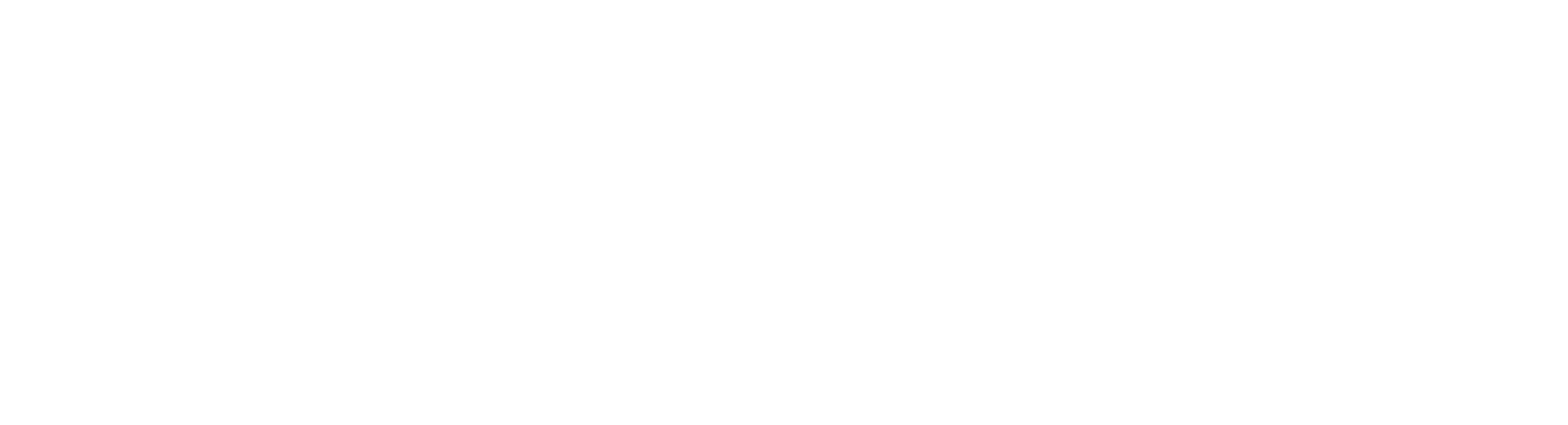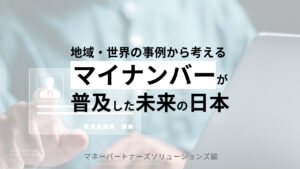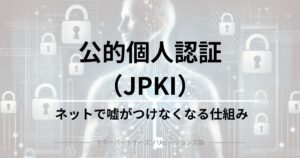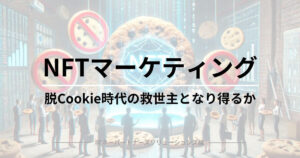次世代の必須インフラ「Web3ウォレット」|未来の覇者の条件とは
「今後、Web3の波に乗れるかどうかで、企業の生き残りが決まる——。」
近年、メルカリ、ソニー、NTTといった国内の大手企業が、Web3ウォレットを核にしたサービス開発に本格的に乗り出しています。 さらに、JREウォレットのような新たなプレイヤーも台頭し、業界の動きはますます加速中です。
しかし、日本の法規制は依然として厳しく、多くの企業が参入を躊躇しているのが現状です。「暗号資産の取り扱いはハードルが高い」「免許取得が難しい」といった声も少なくありません。
ところが、状況は大きく変わろうとしています。 現在、政府は暗号資産の仲介業免許の策定を進めており、これが実現すれば、一気にWeb3ウォレット事業の参入障壁が下がる可能性があります。
「でも、本当に日本でWeb3ビジネスが拡大するのか?」
そんな疑問をお持ちの方もいるでしょう。しかし実際、メルカリやソニー、NTTなどがブロックチェーン技術の導入を積極的に進めています(後半で詳述)。彼らが、こうした先行投資を行っているのは、なぜなのか?
実は、Web3ウォレットは単なる決済ツールではなく、次世代のビジネスインフラとなる可能性を秘めているのです。 本記事では、国内主要プレイヤーの取り組みや、法規制の現状と今後の展望を詳しく解説し、「いま何をすべきか」を考えていきます。
Web3ウォレットとは何か?
Web3ウォレットとは、ブロックチェーン技術を基盤とした次世代のデジタルウォレットです。従来のウォレットと異なり、中央管理者を介さずに資産の保管・送受信ができる点が特徴です。暗号資産(仮想通貨)だけでなく、NFT(非代替性トークン)や分散型ID(DID)といった新しいデジタル資産を管理する役割を果たします。
近年、Web3ウォレットは単なる資産管理ツールを超え、企業のマーケティングや新たなビジネスモデルの構築においても重要な役割を担い始めています。 例えば、ブランド独自のNFTを発行し、ファンとのエンゲージメントを強化したり、トークンを活用したポイントプログラムを構築したりといった活用方法が登場しています。
Web3ウォレットは、従来のWeb2ウォレット(例:Google PayやApple Pay)とは根本的に異なります。
| Web2ウォレット | Web3ウォレット | |
|---|---|---|
| 管理者 | 銀行や決済事業者 | ユーザー自身(非管理型/管理型) |
| 主な用途 | 法定通貨の決済 | 暗号資産、NFTの管理 |
| 本人確認 | KYC(身分証明が必要) | 基本的に不要(非管理型の場合) |
| 取引の透明性 | 事業者に依存 | ブロックチェーン上で透明性が高い |
| 相互運用性 | 事業者のプラットフォーム内 | 異なるサービス間で利用可能 |
これらの特徴から、Web3ウォレットは金融の民主化やユーザー主導の経済圏の創出といった新たな価値を生み出す可能性を秘めています。
厳密に説明すると、Web3ウォレットにはアンホステッドウォレット(非管理型)とホステッドウォレット(管理型)の2種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
- アンホステッドウォレット(非管理型):ユーザー自身が秘密鍵を管理し、完全に自己責任で資産を運用するウォレット(例:MetaMaskなど)
- ホステッドウォレット(管理型):取引所やサービスプロバイダーが秘密鍵を管理し、ユーザーはアカウントを通じて資産を利用するウォレット(例:メルカリのメルコインウォレットなど)
この記事で紹介する事例は、基本的にはホステッドウォレット(管理型)の仕組みを利用しています。
これらを踏まえた上で、国内企業の事例を見ていきましょう。
Web3ウォレットに関する国内企業の取り組み
Web3ウォレットの普及に向け、国内の大手企業も積極的に動き出しています。特にメルカリ、ソニー、NTTといった企業は、すでにブロックチェーン技術を活用したプロジェクトを開始しており、先行者として市場をリードしています。なぜ彼らはWeb3の分野に参入できるのか?その理由を探っていきましょう。
メルカリの「メルカリNFT」が示すWeb3戦略
メルカリは2025年1月、NFT取引市場「メルカリNFT」を発表しました。これは、従来のフリマアプリの延長線上で、デジタル資産を個人間で簡単に売買できる環境を整備する試みです。さらに、Web3ウォレットの導入によって、暗号資産やNFTの取引をよりスムーズに行える体制を構築しました。
この動きからは、メルカリの「既存基盤の活用」→「決済サービスとの統合」→「法規制クリアによる優位性確立」という戦略が見えてきます。まず、数千万人規模のユーザー基盤を活かし、新規参入プレイヤーが直面する市場獲得の壁を容易に乗り越えた。次に、「メルペイ」とのシナジーを生かし、Web3ウォレットをキャッシュレス決済の延長線上に位置づけることで、ユーザーの抵抗感を減らすことに成功。そして、子会社「メルコイン」を通じて暗号資産交換業者の登録を完了し、規制の壁をクリアすることで、Web3事業の展開を可能にしました。
この一連の戦略は、単なるNFT市場の開設にとどまらず、「メルカリ経済圏のWeb3化」を目指した動きと捉えることができます。今後、メルカリがどのようにWeb3ウォレットを発展させていくのかが注目されます。
参考:メルカリ、NFTマーケットプレイス「メルカリNFT」の提供を開始 – メルカリ公式サイト
ソニーのWeb3戦略:ブロックチェーンで築くデジタルエンターテインメントの未来
ソニーは、エンターテインメントやゲーム領域におけるブロックチェーン技術の活用を積極的に推進しています。特に、NFTとデジタルコンテンツの連携に注力し、音楽・映画・ゲームといった資産をWeb3ウォレットと紐づけることで、デジタル所有権の新たな形を生み出す試みを進めています。
この動きからは、ソニーの「既存コンテンツ資産の最大活用」→「ゲーム市場でのマネタイズ強化」→「ブロックチェーン技術による差別化」という戦略が見えてきます。まず、世界的に影響力を持つ音楽・映画・ゲームなどのIP(知的財産)を活用し、NFTを通じた新たな収益モデルを構築。次に、PlayStationの巨大なユーザー基盤を生かし、ゲーム内アイテムやトークンのWeb3対応を進めることで、ユーザー体験と収益の両方を強化。さらに、独自のブロックチェーン技術の研究開発や特許取得を進めることで、セキュリティ面での優位性を確保し、競争力を高める狙いが見えます。
これらの動きは、単なるデジタルアイテムのNFT化ではなく、「ソニー版メタバース経済圏」を形成する布石とも言えます。今後、ソニーがどのようにWeb3技術を駆使し、エンターテインメント業界に変革をもたらすのかが注目されます。
参考:ブロックチェーンを中心とした包括的なWeb3ソリューションの提供を開始 – ソニー公式サイト
NTTデジタルの「scramberry WALLET」が示すWeb3戦略
NTTデジタルは、Web3時代に向けたデジタルウォレット「scramberry WALLET(スクランベリーウォレット)」を提供しています。このウォレットは、暗号資産やNFTの送受信・管理が可能で、Astar、Avalanche、Ethereum、Polygonといった主要ブロックチェーンに対応。すでにiOS版とAndroid版がリリースされており、Web3サービスの入り口として機能します。
この取り組みからは、NTTデジタルの「基盤整備」→「企業連携」→「市場創出」という戦略が垣間見えます。まず、「scramberry WALLET」により安全なWeb3インフラを提供し、ユーザーと企業の参入ハードルを下げる。次に、「web3 Jam」を通じて企業間のNFT活用を促進し、実用的なユースケースを生み出す。そして、経済産業省の実証事業への参画により、公的な枠組みの中でWeb3市場を成長させる基盤を築く。
これらの動きは、単なる金融サービスの拡充ではなく、「日本型Web3エコシステム」を構築するための布石といえます。今後、「scramberry WALLET」がどのような形で社会に浸透していくのか、注目が集まります。
参考:NTT Digital、デジタルウォレット「scramberry WALLET」を提供開始し「スクランベリー」を展開 – 日本経済新聞
新たなプレイヤーの台頭:JRE WALLETがもたらすデジタルサービスの進化
Web3ウォレット市場には今後、多くの企業が参入し、競争が激化していくと予想されます。 前述の3社に次ぐプレイヤーとして、JR東日本が開始した「JRE WALLET」についても触れておきましょう。
JR東日本は、モバイルSuicaと連携するデジタルウォレットアプリ「JRE WALLET」を発表し、2025年1月より提供を開始しました。このアプリは、Suicaの使用履歴に基づいたクーポンの提供や、クーポンの受け渡し機能を備えています。さらに、今後のアップデートで、ユーザーの同意に基づき、共創企業へSuicaの利用データを提供する仕組みも導入される予定です。
この取り組みは、JR東日本の「Suicaの利便性向上」→「デジタルサービスの拡張」→「企業とのデータ連携強化」という戦略の一環と考えられます。まず、既存のSuicaユーザーに向けて新たなデジタル特典を提供し、利用価値を高める。次に、クーポン配布やデータ連携を通じて、企業との協力を強化。最終的には、交通だけでなく、買い物やエンターテインメントなど、生活全般でのSuicaの活用機会を広げる狙いがあると考えられます。
今後、企業との連携がどのように進化し、ユーザーにどのような価値を提供していくのかが注目されます。
参考:JR東日本、新たなデジタルアプリ「JRE WALLET」開始 – Impress Watch
Web3ウォレットの普及における法的背景と規制
Web3ウォレットの普及において、日本の法規制は大きな障壁の一つとなっています。暗号資産(仮想通貨)の取引には厳格なルールが設けられており、企業がWeb3関連事業に参入するためには、法律の枠組みをクリアする必要があります。
しかし、近年の規制緩和の動きにより、「暗号資産等取引に係る仲介業」という新たな免許制度が検討されており、これが実現すれば市場の参入障壁が大幅に下がる可能性があります。 ここでは、現在の法規制の概要と、今後の見通しについて解説します。
日本におけるブロックチェーン関連の法規制
日本では、暗号資産やNFTに関連する取引は、金融庁の厳しい監督下にあります。 主要な規制として以下の法律が存在します。
- 資金決済法(改正済み)
暗号資産(仮想通貨)を擬似的な「決済手段」として活用できるが、取り扱いには暗号資産交換業の登録が必要。メルカリのように暗号資産取引を事業化する企業は、この登録を受けている。 - 金融商品取引法
トークン化された証券(STO)は、金融商品として扱われる。NFTは原則として証券に該当しないが、投資目的のものは規制対象となる可能性がある。 - 銀行法・資金移動業法
一般企業が銀行業務を行うには、銀行業免許が必要。ただし、「銀行代理業」として登録すれば、銀行業免許なしで一部の金融サービスを提供可能。
このように、日本では暗号資産やWeb3ウォレットに関する規制が厳しく、多くの企業が参入を躊躇する原因となっています。
メルカリで擬似的にビットコイン決済ができるのは、ビットコインの売却とメルペイへの入金処理が瞬時に行われているためです。ヘルプセンターにも以下のような説明があります。
メルカリ内のお買い物にビットコインの使用を選択した場合、保有しているビットコインを売却し、売却して得たお金をメルペイ残高へ自動でチャージ(入金)することで、メルカリのお買い物の支払いに使用する決済方法です。
ビットコインの使用 – メルカリヘルプセンター
法規制の今後とビジネスチャンス
日本におけるWeb3ウォレットの発展には、今後の法規制の動向が大きく影響を及ぼすと考えられます。特に注目されているのが、現在政府が検討を進めている「暗号資産等取引に係る仲介業」の創設です。これは、これまで金融庁による厳格な「暗号資産交換業者」の登録が求められていた枠組みに対して、新たな選択肢を与えるものであり、多くの企業にとってWeb3市場への参入を現実的なものに変える可能性があります。
そもそも、なぜこうした規制緩和が求められているのでしょうか。それは、現在の制度があまりに高いハードルとなっており、イノベーションの芽を摘んでしまっているからです。日本のスタートアップや既存企業の多くが、Web3への関心を持ちながらも、法的な不確実性や事業リスクの高さゆえに踏み出せずにいます。つまり、制度の整備は、技術の可能性をビジネスに接続するための「地ならし」とも言えるわけです。
ここでは、この新たな規制がもたらす変化と、それによって広がるビジネスチャンスについて、具体的に解説していきます。
参考:資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料 – 金融庁
暗号資産等仲介業免許の策定動向
現在、日本では暗号資産を扱うには、金融庁の「暗号資産交換業者」として登録する必要があります。この登録には厳格な審査と高額な資本要件が求められるため、特に中小企業やスタートアップにとっては非常に大きな負担でした。
しかし、新たに検討されている「仲介業免許」は、企業が暗号資産を直接保有せずとも、取引の仲介という形でサービス提供ができるようにするものです。これは、暗号資産を「預からない」「保有しない」という点でリスクを大幅に低減できる仕組みです。その結果、これまで参入をためらっていた企業が、Web3事業にチャレンジしやすくなると期待されています。
仲介業免許がもたらす変化
この免許が導入されれば、以下のような変化が現実のものとなるでしょう。
- Web3サービスを展開しやすくなる
従来、暗号資産を取り扱うには金融庁の厳しい基準をクリアする必要がありました。仲介業免許の枠組みであれば、その負担が軽減され、スタートアップや非金融系企業も参入しやすくなります。 - 企業の参入障壁が下がる
暗号資産を自社で保有しない設計とすることで、事業リスクやコンプライアンス面の負荷が大幅に軽減されます。資金や人材の制約がある中小規模の企業にとっては、これは極めて大きなメリットです。 - デジタル資産を活用した新たなビジネスモデルが登場する
例えば、企業が独自のトークンを発行したり、NFTを活用した顧客ロイヤルティプログラムを展開したりする動きが加速するでしょう。これまでのように、規制の“壁”に阻まれることなく、アイデアをスピーディに形にできる土壌が整いつつあります。
仲介業免許がもたらすビジネスチャンス
この新しい枠組みは、単なる制度改正ではなく、日本企業がグローバルなWeb3競争に加わるための“起爆剤”でもあります。実際に、次のようなビジネス分野での急速な展開が予想されます。
- ゲーム業界におけるNFT・トークンの活用
ゲーム内で使用されるアイテムや通貨をトークン化し、プレイヤー間で売買・交換できるようにする動きは、すでに海外では一般化しつつあります。日本企業がこれに続くには、規制環境の整備が不可欠でした。 - 企業のポイントシステムのWeb3化
既存のポイントをトークンとして発行し、複数企業間での相互利用を可能にする仕組みが現実味を帯びてきます。たとえば、異なる業種の企業が共通トークンを導入すれば、消費者はポイントの“垣根”を越えて利用できるようになります。
仲介業免許の整備は、Web3を「限られた一部のプレイヤーの世界」から、「誰もが参入できるビジネスフィールド」へと広げるための重要な一手だということです。
今後、この分野の制度整備が進めば、日本発のWeb3イノベーションが世界をリードする日も、そう遠くないのかもしれません。
まとめ
本記事では、Web3ウォレットの可能性と、それを支える日本の主要企業の取り組み、法規制の動向、そして今後のビジネスチャンスについて解説しました。
メルカリ、ソニー、NTTデジタルといった企業は、すでにWeb3ウォレットを活用したサービスの開発を進めており、国内市場は確実にWeb3時代へとシフトしつつあります。 さらに、JREウォレットのような新たなプレイヤーの台頭や、政府の暗号資産等仲介業免許の策定といった動きもあり、今後市場の成長スピードはさらに加速するでしょう。
Web3ウォレットは単なる決済手段ではなく、デジタル資産管理の新たなインフラとして、次世代のビジネスを支える存在になりつつあります。
今後、企業がこの市場で競争優位性を確立するためには、法規制の動向に対応した戦略を立てることや、暗号資産やNFTを活用した新たなビジネスモデルの模索が求められます。
今、日本国内でWeb3ウォレットに本格的に取り組めば、次世代の覇権を握るチャンスを得ることができるはずです。
市場はすでに動き出しており、競争に乗り遅れることが最大のリスクとなる時代が到来しています。
企業の経営者・マーケティング担当者として、今すぐできることは何か?
その答えを考え、いま行動を起こすことこそが、未来のビジネスを勝ち取る第一歩となるでしょう。
私たちマネーパートナーズソリューションズも、ブロックチェーン技術に大きな可能性を感じており、さまざまな取り組みを行っています。金融ITベンダーとして培った経験から、一般的に「難しい」と感じる金融関連法令に対応した業務整理についてもご相談いただけます。Web3時代の戦略展開を考えるパートナーとしてお手伝いさせてください。
以下のフォームより、お問い合わせをお待ちしています。