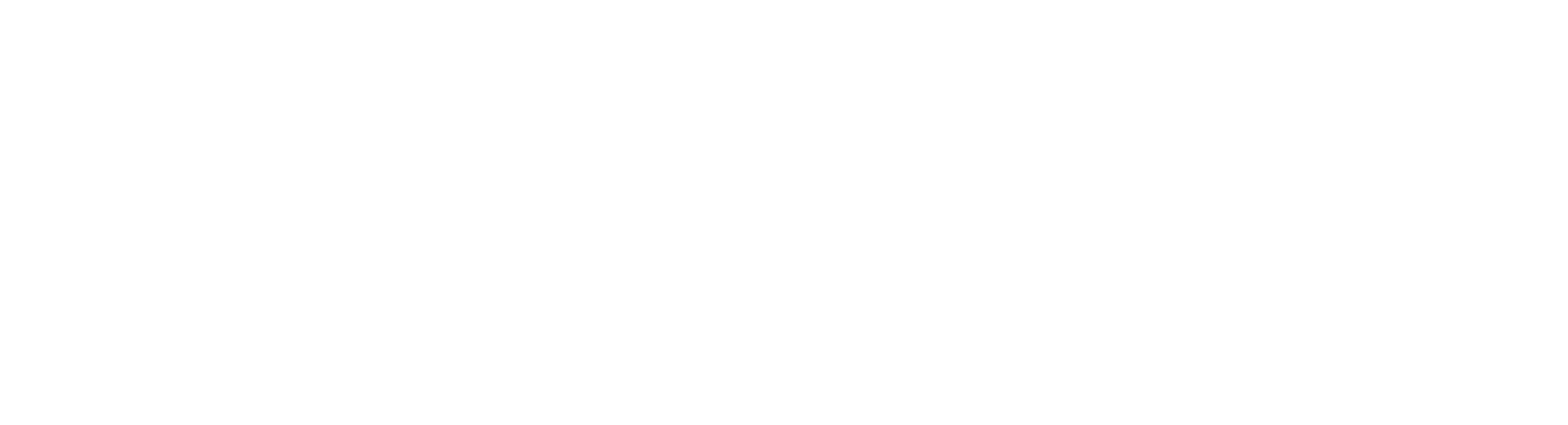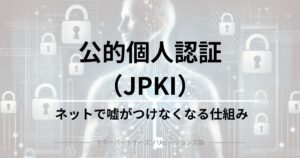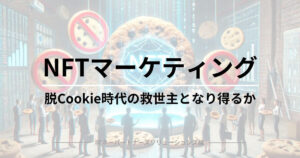地域の事例から考えるマイナンバーがもたらす未来の社会とは?
もしマイナンバーが、あらゆる場面で便利に活用される未来が訪れたら、どのような暮らしが実現するでしょうか。
システムエラーやセキュリティなど、何かとマイナス面ばかりがクローズアップされがちなマイナンバーですが、本格的に普及すれば生活上での利便性は格段に上がります。
マイナンバーによる個人認証は、行政機関や医療機関でも正確で迅速な手続きを可能にします。身分証や書類を何度も提示する煩わしさがなくなり、なりすましによる不正防止にもつながります。
行政機関にとっても、手続きの簡略化や、給付・還付金の迅速な受け渡しが可能になるなど、大きなメリットがあります。
本記事では、架空の街「A町」を舞台に、マイナンバーが普及した「少し先の未来の日本」をシミュレーションします。
その町では、住民がスマートフォンに搭載されたマイナンバーを使い、公共施設や交通手段を利用し、健康促進イベントに参加しながらポイントを貯め、地元商店での買い物に使える仕組みが整っています。行政手続きの効率化だけでなく、地域経済やコミュニティの活性化にもつながる万能ツールとして、マイナンバーが力を発揮しているのです。
「A町」の未来像を通じて、日本社会全体でマイナンバーカードがもたらす可能性を考えてみましょう。
ある町の暮らし:マイナンバーカードで変わる日常

ここでは、架空の街「A町」を例に、マイナンバーが暮らしの中でどのように役立つかを具体的に描いてみます。住民一人ひとりの生活が便利になるだけでなく、地域全体が効率的に運営される未来をイメージしてみてください。
朝のルーチン:カードで快適なスタート
A町の住民である佐藤さん一家。小学生の娘が登校し学校のゲートにスマートフォンをかざすと、母親のスマートフォンに「学校に到着しました」と通知が届きます。安心感を胸に、母親は家を後にします。
昼間の利用シーン:健康促進と地域の支え合い
高齢の山田さんは午前中、町のコミュニティセンターで健康体操教室に参加。教室終了後にスマートフォンを教室の端末にかざし、マイナンバーアプリで健康ポイントを獲得します。このポイントは、週末に地元商店で特産品を購入する際に利用できる仕組みです。
昼間の利用シーン:補助金をダイレクトに給付
佐藤さんの息子は学校での成績優秀者に贈られる学習補助金を受け取る日です。学校からの通知で知らせを受けた佐藤さんは学校帰り、スマートフォンのマイナンバーアプリをコンビニの専用端末にかざし、補助金が即時にチャージされるのを確認しました。これを家族での買い物や学習教材の購入に役立てる予定です。
夕方の買い物:地域通貨で経済を循環
佐藤さん一家は夕方、町の商店街で買い物を済ませました。スマートフォンにチャージした地域通貨で支払いを行います。この地域通貨は、日々の歩数達成や健康施設利用時に貯めた「健康ポイント」として獲得したものです。健康活動と地域経済が結びつくこの仕組みにより、商店街はさらに活気づき、A町全体の経済循環が促進されています。
朝日町の事例と諸外国の先進事例

ここまで書いてきたA町の未来像は、実はすでにいくつかの地域や国で実現されている事例が元になっています。海外のインド、エストニア、シンガポール、アメリカ、ドイツの取り組みと、日本の富山県朝日町です。
それぞれ見ていきましょう。
インド:デジタル認証の革新と福祉改革
インドでは、日本のマイナンバーにあたる共通番号「Aadhaar(アーダール)番号」を活用し、税務や社会保障など多岐にわたる行政サービスで効率的な個人認証が行われています。この番号は、顔写真、指紋、虹彩という生体情報と紐づいており、12桁の固有番号として発行されます。2024年には国民の約9割、13億人が登録を完了するなど、世界最大級の規模を誇ります。
Aadhaar番号の導入前、多くの貧困層は戸籍がなく、公共福祉サービスを受けられませんでした。しかし、アーダールの普及により、誰でも簡単に身分証明が可能となり、銀行口座の開設や給付金の受給ができるようになりました。
この仕組みは、不正防止に役立ち、政府が提供する福祉サービスの公平な分配を実現しています。さらに、教育や医療を含む多分野で、デジタル公共インフラの中核として利用されています。
加えて、インドは「India Stack」というオープンAPIプラットフォームを通じ、Aadhaar番号を基盤とした幅広いサービスを展開しています。この仕組みは行政と民間の垣根を越え、ユーザーの利便性を向上させています。さらに、この成功事例を基に、モロッコやフィリピンを含む新興国への生体認証技術の輸出も進めており、今後5年以内に50カ国・10億人への導入を目指しています。
一方で、Aadhaarの生体情報データは暗号化されて管理されていますが、個人情報の漏洩リスクが懸念されています。それでも、インドの取り組みは、貧困層の生活向上とデジタル社会の実現に大きく貢献しており、国民にとって不可欠な存在となっています。
エストニア:デジタル政府のパイオニア
エストニアでは、e-IDカードとデータ交換プラットフォーム「X-Road」を活用することで、住民が多岐にわたる行政サービスをオンラインで簡単に利用できる環境が整っています。
例えば、住民は自宅にいながら医療記録を確認し、処方箋をオンラインで取得することが可能です。また、教育分野では、学校との連絡や子供の成績確認がオンラインで行えるため、保護者の負担が軽減されています。金融サービスにおいては、ローンの申請や納税が迅速に処理され、手続きにかかる時間と労力が大幅に削減されました。
この仕組みにより、住民は日常生活に必要な多くの手続きが一元管理され、効率的な時間管理が可能となっています。
シンガポールのSingpassと医療連携
シンガポールのSingpassは、政府や金融、医療サービスを一括で利用可能にするデジタルプラットフォームです。
Singpassを利用することで、住民は納税やビザ申請などの政府手続きから、銀行口座の管理や保険契約の確認まで、一つのログインでシームレスにアクセスできます。
特に医療分野では、住民が自身の医療履歴や予約状況を簡単に確認し、診察予約や補助金申請をオンラインで完結できる仕組みが整備されています。高齢者や多忙な家庭を持つ住民にとって利便性が高く、健康管理の意識向上にも寄与しています。
アメリカのSSNと本人確認システム
アメリカでは、社会保障番号(SSN)を基盤とした本人確認システムが住民の利便性を向上させています。
例えば、雇用時の背景確認や銀行口座開設に必要な本人確認が、リアルタイムで正確に行える仕組みが整っています。
また、低所得者向け医療補助金の申請も、SSNを通じて迅速に行うことが可能です。住民は煩雑な書類手続きから解放され、短時間で必要なサービスを受けることができます。
ドイツ:プライバシー保護に重点を置いたeID
ドイツのeIDは、住民に利便性とプライバシー保護を両立したサービスを提供しています。
たとえば、オンラインショッピングや公共サービスの利用時に、住民は個人情報を最低限の範囲で安全に提供できる仕組みを利用しています。住民は個人情報の漏洩リスクを心配することなく、デジタルサービスを安心して利用できます。
さらに、eIDはヨーロッパ経済圏(EEA)内での認証にも対応しているため、他国での滞在時に公的手続きや医療サービスをスムーズに受けることが可能です。このような国際的な互換性も、住民にとって大きな魅力となっています。
海外事例については、デジタル庁が配布している以下の資料を参考にしています。
地域の生活インフラを支える朝日町の「LoCoPi」
日本でも、いち早くデジタル個人認証を取り入れている地域があります。
富山県朝日町では、マイナンバーカードを活用した「LoCoPi(ロコピ)」が、住民の生活を支える仕組みとして機能しています。
住民は、図書館や公共施設の利用時にカードを端末にかざすだけで手続きが完了し、健康イベントへの参加で貯めたポイントを地元商店での買い物に使うこともできます。また、見守り機能により、子供の登下校や高齢者の外出時に家族へ通知が送られるため、安心感が高まっています。
さらに、行政はカードの利用データを活用して、公共サービスを効率的に提供し、地域経済の活性化や住民同士のつながり強化にもつなげています。
同町のマイナカードの普及率は2023年末時点で80.8%と全国の73%を上回るなど、活用度合いが数字としても現れています。
カギを握るマイナンバーのスマートフォン搭載

日本でも、マイナンバー普及の土台が整備されつつあります。
これまではAndroid(一部機種非対応)でしか利用できなかったマイナンバーカードの機能が、2025年春にはiPhoneにも搭載されるのです。
前述のA町のシミュレーションでも、住民は様々な場所でスマートフォンを取り出し、専用の端末にかざすことでマイナンバーの機能を活用していました。この未来は、すでに現実のものになりつつあるということです。もっと未来では、ウェアラブル端末にも搭載され、より身近なものになるかもしれません。
さらに、マイナンバーに保険証や運転免許証の機能も一体化が進んでいます。仕組みが正しく運用されれば、スマートフォン1つ持っていれば、オンライン・オフラインを問わず「自分自身である」ということを証明できるようになります。
別の記事でも書いた、「デジタルID」が実現する未来に向かい、技術は着実に進歩しています。
まとめ:未来への展望
国内外の先進事例から得たヒントをもとに、マイナンバーカードが普及した未来の社会をシミュレーションしてきました。
現在、日本では紐付け不備やマイナ保険証への強引な切り替えなど、不安や不満の声が多く聞かれます。しかし、マイナンバー制度の普及は、住民、行政、企業に多大なメリットをもたらす可能性を秘めています。
住民にとっては、図書館や公共施設の利用がカード1枚で完了する利便性に加え、健康ポイントや補助金の迅速な受け取り、見守り機能による安心感が得られます。
行政機関は、住民データを活用して公共サービスを効率化し、地域経済の活性化や限られた資源の最適配分を実現可能です。
また、企業にとっても、採用や金融取引における本人確認が簡略化され、業務効率や顧客体験が向上するでしょう。
一方で、普及にはさまざまな課題が立ちはだかっています。特にプライバシー保護や個人情報漏洩への懸念は根強く、マイナンバー普及の大きなハードルとなっています。
また、高齢者やデジタル技術に不慣れな人々へのサポート体制が不十分で、対応格差を生む可能性も指摘されています。さらに、システム間の連携不足や導入コストの高さも、普及を妨げる要因の1つです。
マイナンバー制度を社会全体に浸透させるには、住民が利便性を実感できる具体的なインセンティブを提供し、信頼性の高い運用体制を整えることが鍵となります。
国内外の成功事例を参考にしながら、制度を進化させていくことで、行政サービスの効率化と地域社会の活性化、そして住民一人ひとりが安心して暮らせる未来が現実のものとなるでしょう。
私たちマネーパートナーズソリューションズでも、「理想の未来」を実現するため、テクノロジーの力でサポートしたいと考えています。
ご興味のある行政機関、企業担当者様は、ぜひ以下のフォームよりお問い合わせください。