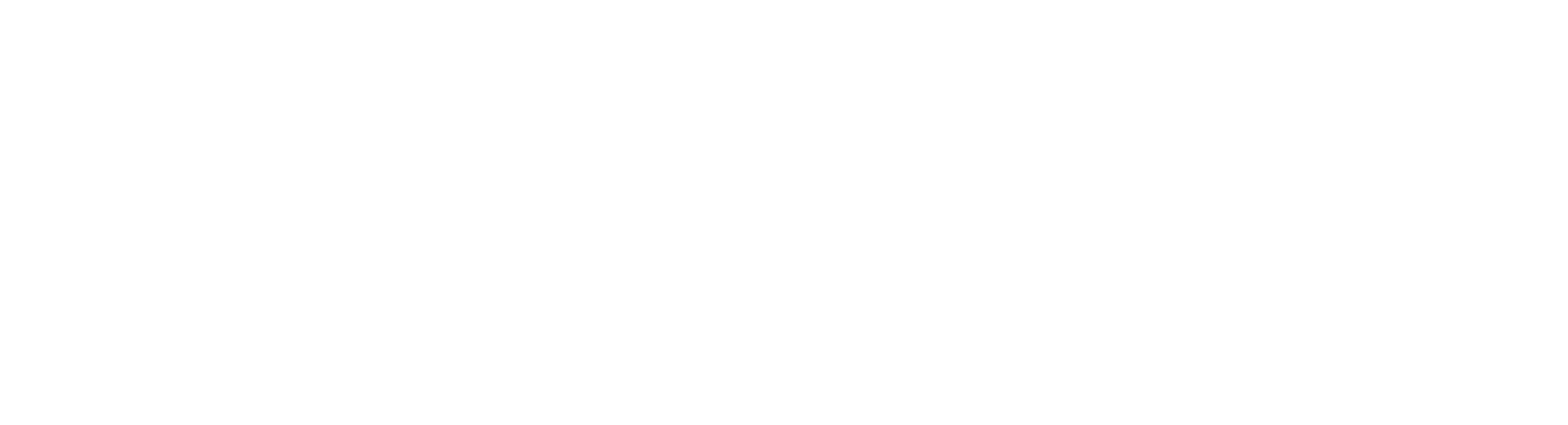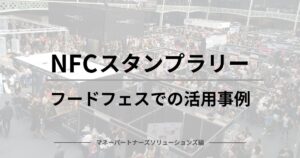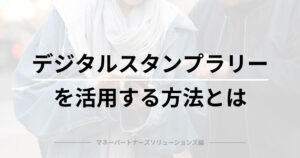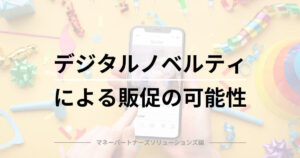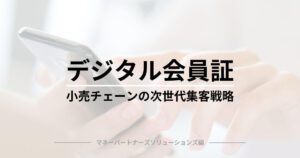「健康ポイント」のメリット・導入方法|自治体から企業まで活用
健康ポイント制度とは、自治体の住民や会社の社員の健康意識を高めるためにインセンティブを与える制度のことです。
例えば、期間内の歩数やスポーツイベントなどへの参加状況に応じてポイントを付与し、たまったポイント数に応じて商品と引き換えるというような仕組みです。
医療費の増加による財政の圧迫に悩む自治体や、同じように財政難の緩和につなげたい企業の健康保険組合が取り入れています。企業の場合には、他にも従業員の意欲や定着率を高めるために利用されているケースもあります。
健康ポイント制度は、アナログのポイントカードを使った仕組みを展開している場合も多いことでしょう。しかし、こうした場合には参加者が高齢者に偏ることや、健康改善意思のない無関心層を取り込めないことが課題となっています。
こうした課題に対応すべく、健康ポイントをスマホアプリとして提供する自治体や企業も増えてきました。近年はスマートフォンが社会インフラと呼べるレベルにまで普及したことで、若年層から高齢層までの全ての層に対してデジタルでのサービス提供も可能になりました。
この記事では、健康ポイントを導入したい自治体や企業の担当者向けに、健康ポイントの導入事例や導入方法について解説します。
健康ポイント導入のメリット
まずは、健康ポイントを導入することで受けられるメリットについて整理しておきます。
健康ポイントで得られるメリットは以下の3点です。
- 医療費の削減
- 地域経済の活性化(自治体)
- 社員のモチベーションアップ(企業)
それぞれ見ていきましょう。
医療費の削減
健康ポイント制度は、市民の健康寿命を伸ばすことで、間接的に医療費削減につながります。
健康ポイントは、ウォーキングや市の運営するフィットネスクラスへの参加、健康診断の受診など、健康に良い活動を行うとポイントが付与されるという仕組みです。ポイント獲得が市民が健康的な生活を送るための動機付けとなり、自然と健康的な生活を送れるようになるということです。
インセンティブを付与することの大きな狙いは、健康への無関心層を取り込むことです。
地域経済の活性化(自治体)
地域の店舗やサービスが健康ポイントの利用先となることで、地元経済の活性化にも繋がります。市民がポイントを使うために地域内の店舗を訪れ、新たな消費を生むことになります。
単なる医療費の削減という守りの効果だけでなく、地域全体の規模を大きくするという恩恵も期待できるということです。
社員のモチベーションアップ(企業)
企業の場合には、従業員の就業意欲や定着率を高めるために健康ポイントを利用しているケースもあります。
従業員の健康は、企業の競争力の源泉です。心身を健康に保つことで従業員の仕事に対する意欲を高め、生産性の向上につながるということです。
さらに、健康への取り組みは従業員の定着率向上にもつながります。これはインセンティブのためだけではありません。心身ともに安全が保障された場所には人がとどまりやすくなるためです。
健康ポイントの導入事例
健康ポイント事業は、都道府県や市町村などの自治体で行っているものが代表的ですが、健康経営の取り組みの一環として企業でも取り入れられています。
自治体での事例:福岡県「ふくおか健康ポイント」
福岡県は、県内共通のポイントアプリを展開しています。
ポイントは、歩数以外にもイベント参加や健康診断受診、アプリの健康状態を記録することでも付与されます。
ポイントを貯めると、協力店舗で利用できるクーポンへの引き換えや抽選会への応募、県内各市町村が独自に提供している特典を受けることができます。
企業での事例
健康ポイントを福利厚生として取り入れている企業もあります。
例えば日本電信電話(NTT)では、従業員に歩数や体重・血圧を記録してもらい、毎日配信される健康対策ミッション(フィットネスなど)を達成してもらうことでポイントを付与する取り組みを行っています。
健康ポイントの導入方法
ここでは、健康ポイントの導入方法について解説します。歩数計やスタンプカードなどを使ったアナログ運用からの移行を考えている方にも参考になるはずです。
健康ポイントの導入方法には、大きく分けて以下の2つの方法があります。
- 独自アプリの開発
- LINE拡張機能の利用
それぞれメリット・デメリットを押さえた上で、どのような方法を取るか検討しましょう。
独自アプリの開発(パッケージのカスタマイズ)
最も柔軟性が高く、必要な機能をカスタマイズ性高く実装できるのが、独自アプリ開発のメリットです。
事例で紹介した「ふくおか健康ポイント」も独自アプリを開発し展開しています。
デメリットとしては、開発に費用や時間がかかる点や、ユーザーに浸透させるまでの販促にエネルギーが必要な点です。はじめから機能をたくさん盛り込むのではなく、必要最小限の機能に絞って開発するというのも1つの方法です。
また、スマートフォン端末のセンサーで取得した歩数データなどを連携させるため、通常のアプリ開発よりも技術要件が高くなります。外部接続やセキュリティ対策などの経験豊富なベンダーを選ぶことも重要です。
LINE公式アカウントを利用する
健康ポイントを最も手軽に導入できる方法の1つがLINE公式アカウントです。
LINEはメッセージアプリですが、ポイントやクーポンなどの拡張機能を導入することができます。LINEのトークルーム内のメニューを拡張する「リッチメニュー」も活用し、ユーザーの行動を促すような施策も可能です。
LINEは、日本では「インフラ」と呼べるレベルまで浸透しているため、ユーザビリティも良いというメリットもあります。
LINEというメッセージアプリのトークルームの1つとして提供されるもののため、他のメッセージに埋もれやすいというデメリットがあります。習慣化してもらい継続して使ってもらうためには工夫が必要です。
独自アプリの開発と同じく、端末の歩数データなどを連携するためには追加で開発が必要になります。
私たちマネーパートナーズソリューションズでは、金融システムの開発で培った知見を活かし、健康ポイント構築のお手伝いも承っています。まずは以下のフォームからお問い合わせいただき、お話をお聞かせください。
健康ポイント導入の際の注意点
健康ポイントの導入にあたっては、参加しやすいシステム設計・制度設計が重要です。
自治体の全住民、企業では全社員が対象者となるため、幅広い年齢層に向けた「使いやすい仕組み」である必要があります。「アプリを作る」というのが目的ではなく、ポイントの獲得方法や利用先を明確にするなど制度としてうまく回る仕組みを整えなければなりません。
健康ポイント制度は、「健康寿命を伸ばす」というゴールの特性上、結果が目に見えるまでに数年単位の時間がかかります。状況を見て都度調整するという対応がしづらいため、導入時のシステム設計や制度設計が重要になるということです。
まとめ:健康ポイントの将来展望
健康ポイント制度について解説してきました。
「端末の歩数データを連携できるアプリを作る」という目に見えるツール自体を作るのは、開発費用さえかければすぐに実現可能です。
しかし、「利用者の健康寿命を伸ばす」という目的を実現させるためには、使い続けてもらうための制度設計や長期的な戦略を考える必要があります。
健康ポイントの今後の展望としては、「デジタルID」との融合も考えられます。内閣府が進める「Society 5.0(ソサエティ 5.0:サイバー空間と現実空間を高度に融合させた、未来の人間社会像)」の一環として「デジタルIDウォレット」の整備が進んでいます。これは、スマートフォンなどの端末上で身分証明や持ち主の属性情報を管理できるという仕組みです。
将来的には、このデジタルIDウォレットをキーとすることで、なりすましやプライバシーの侵害を防ぎつつ利便性の高い仕組み(自己主権型ID)が整備されることも期待できます。
こうした仕組みにより、例えば医療機関との病理検査等のデータを連携し、完全な匿名の統計データでは判断できない病気のリスクを発見することも可能になります。デジタル技術の進歩が、「健康寿命を伸ばす」という本質的な取り組みにもつながるということです。
こうした時流に対応するためには、早い段階からシステムの運用ノウハウを貯めておくことが理想です。できるところから取り組んでいきましょう。
マネーパートナーズソリューションズでも、こうした未来も見据えた上で、拡張性の高いシステム作りのお手伝いができればと考えています。興味がおありの方は、以下のフォームからお問い合わせください。